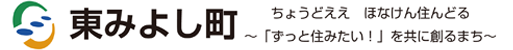国民健康保険税とは
国民健康保険税とは、みなさんの健康を守るための医療事業を運営するために納めていただく税金です。会社の社会保険や共済組合に加入している方は、給料から保険料を差し引かれていますが、それと同じように国民健康保険に加入している方は、税金として納めていただくものです。
納税義務者について
国民健康保険に加入している世帯の世帯主が納税義務者となります。また、世帯主自身が社会保険や共済組合、後期高齢者医療制度などに加入している場合でも、その世帯の中に国保加入者がいるときは、その世帯主を納税義務者とします。(これを擬制世帯主といいます。)
国保税率及び課税額等について
国保の税額は、医療分、介護納付金分、後期高齢者支援金分を合わせた額となります。それぞれの税額は、加入者各々の所得に応じて課税される「所得割」、資産に応じて課税される「資産割」、被保険者1人ずつに必ず課税される「均等割」、世帯に課税される「平等割」を算出した合計額となっています。(ただし介護納付金分は、介護保険の第2号被保険者(40~64歳の方)についてのみ算定します。)
| 区分 | 医療分 | 介護納付金分 | 後期高齢者支援金分 | 算出方法 |
|---|---|---|---|---|
| (0~74歳) | (40~64歳) | (0~74歳) | ||
| 所得割 | 9.05% | 2.13% | 2.50% | 課税対象額(※1)×税率 |
| 資産割 | 23.20% | 4.00% | 8.00% | 固定資産税額(※2)×税率 |
| 均等割 | 24,500円 | 7,200円 | 6,700円 | 被保険者1人につき |
| 平等割 | 22,000円 | 4,200円 | 5,700円 | 1世帯につき |
| 課税限度額 | 650,000円 | 170,000円 | 240,000円 |
※1.課税対象額とは、被保険者ごとの総所得金額等(前年の総所得金額及び山林所得金額並びに申告した分離課税の株式・長期譲渡所得金額・短期譲渡所得金額等の合計)から基礎控除の43万円を控除した額のことです。
※2.固定資産税額とは、加入者の本年度固定資産税額のうち、土地及び家屋に係る分(共有分を含む)のことです。
(注1)加入された時点で40歳未満の方の介護保険料は、40歳到達の翌月に更正分の納税通知書を送付します。
(注2)世帯の被保険者数と所得状況により軽減が受けられる場合があります。
納期について
|
普通徴収 (納付書払い・口座振替) |
特別徴収 (年金からの天引き) |
|
| 4月 | 第1期(仮徴収) | |
| 5月 | ||
| 6月 | 第2期(仮徴収) | |
| 7月 | 第1期(口座振替分全期) | |
| 8月 | 第2期 | 第3期(仮徴収) |
| 9月 | 第3期 | |
| 10月 | 第4期 | 第4期(本徴収) |
| 11月 | 第5期 | |
| 12月 | 第6期 | 第5期(本徴収) |
| 1月 | 第7期 | |
| 2月 | 第8期 | 第6期(本徴収) |
| 3月 |
- 各納期限及び口座振替日は各月の月末(12月は25日)です。ただし、休日の場合は翌営業日になります。
- 上記納期以外に臨時的に課税される場合(随時)があります。
年金特別徴収について
次のア~エのいずれにも該当する場合は、国保税が世帯主の年金から天引き(特別徴収)されます。
ア.世帯主が国民健康保険の被保険者であること(擬制世帯主を除く)
イ.世帯内の国民健康保険被保険者全員が、65~74歳であること
ウ.世帯主が年額18万円以上の年金を受給していること
エ.国民健康保険税と介護保険料の合計が、年金受給額の2分の1を超えないこと
- 4、6、8月は仮徴収(前年度2月の国保税額と同額を徴収します。)
- 10、12、2月は本徴収(前年中の総所得額により、国保税の年税額の本算定を行い、算出した年税額から仮徴収した合計分を差し引いた、残りの税額を3回に分けて特別徴収します。)
- 世帯主が75歳に到達する年度においては、普通徴収(納付書払い・口座振替)となります。
- 年金特別徴収は申出書を提出していただくことで口座振替へ変更できる場合があります。
国民健康保険税納付方法変更申出書.doc (DOC 18KB)
詳しくは税務課までお問い合せください。